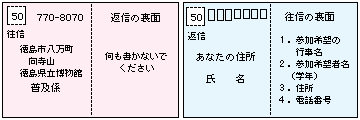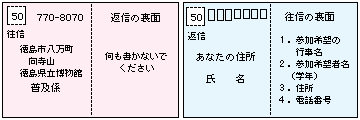
徳島県立博物館の催し物ご案内です.ふるってご参加ください.
森の中や草原だけでなく,田んぼや川などの水の中にもいろいろな生き物がたくさんすんでいます.小さな昆虫たちは,砂地や石のあるところなど,その場所の状態によってすんでいるものがちがいます.また,水の汚れ具合などによっても,そこにすむ虫たちはちがってきます.文化の森総合公園の前の川にはどんな昆虫がすんでいるのか一緒に調べてみましょう.そして,そこにいる昆虫たちはどんな環境を好むのかを覚えておくと,自分の身の回りの水にすむものとの比較もできるようになりますよ.
○日 時 8月1日(土)午前10時〜12時
○場 所 文化の森総合公園前の園瀬川
○講 師 徳山 豊(森山小・教頭)
大原 賢二(博物館自然課長)
○対 象 小学生から一般(小学生は保護者同伴)
○定 員 35名
○申込方法 別記の方法で,7月22日(水)までにお申し込みください。ひざくらいまで水に入れる服装.タオル,帽子,筆記用具などを持参して下さい.
「名もない花が道ばたに咲いていた」というフレーズにはロマンチックなひびきがありますが,我々の身近に咲く花にはほとんど名前がついています.しかし,その名前を調べようとしてもたくさんある図鑑のどれをみれば良いのか迷ってしまいます.そして,そうこうしているうちに花はどんどん枯れていってしまいます.
そうならないためには,まず,おし葉標本をつくり,咲いていた状態をできるだけ保存します.次に検索法を使って,種類を絞り込むことによって名前を調べやすくします.その方法を実際の植物を使って実習します.
○日 時 8月2日(日)午前10時〜午後4時
○場 所 博物館3階 実習室
○講 師 小川 誠(博物館主任学芸員)
○対 象 小学生から一般(小学生は保護者同伴)
○定 員 30名
○申込方法 別記の方法で,7月23日(木)までにお申し込みください。
昆虫の色と形はおどろくほどいろいろなものがあります.ハデな色をしたものや,周りとほとんど同じような色と形をしたものなど,とても生き物とは思えないようなものもいます.ハデな色や目立たない色と形にはそれなりの理由があります.それは敵から自分を守るために,相手に警告をあたえたり,逆にそこにいることをわからないようにしているのです.そのようなものを擬態(ぎたい)と呼んでいますが,チョウやガのなかまにもそのようなものは多く見られます.展示されているこれらの標本を見ながら,チョウとガの擬態のいろいろと,その意味を考えてみましょう.
○日 時 8月8日(土)午後2時〜午後3時
○場 所 博物館3階 講座室
○講 師 大原 賢二(博物館自然課長)
○対 象 小学生から一般
○定 員 50名
※申し込みは必要ありません(直接会場へおこしください)。
「火」は人間の生活を大きく変え、豊かにしてきました。人類の歴史の中で「火」との出会いはもっとも大きな出来事のひとつだったのです。では、大むかし、現代のようにマッチやライターなどがなかったころ、人びとはどうやって火をつくりだしていたのでしょうか?発掘調査によって見つかる出土品や古くから伝わっている民俗例などから考えると、ものをこすりあわせたときの摩擦熱を利用する方法と、火花による方法があったようです。
この体験学習では、これらの方法で実際に火おこしに挑戦して、大むかしの人びとの生活の一部を体験してみようと思います。
○日 時 8月9日(日)午前10時〜12時
○場 所 博物館3階 実習室と屋外
○講 師 魚島 純一(博物館学芸員)
○対 象 小学から一般(ただし、小学生は保護者同伴)
○定 員 30名
○申込方法 別記の方法で,7月30日(木)までにお申し込みください。別記の方法で、7月30日までにお申し込みください。
必ず、保護者の方のお名前もお書きください(定員は保護者も含めて30名です)。
海水浴場でひろった貝殻や磯でつかまえた生きている貝も,ちゃんと標本として保存しておけば,いい夏の思いでになります.当日は採った貝をお持ちいただいて,じょうずな標本のならべ方,ラベルの作り方などを実習します。準備として,採った場所,日付,採った人の名前を記録しておいてください。貝の名前調べについては,8月26日の「標本の名前を調べる会」でおこないます。
○日 時 8月22日(土)午後2時〜午後4時
○場 所 博物館3階 実習室
○講 師 田辺 力(博物館主任学芸員)
○対 象 小学生から一般
○定 員 40名
○申込方法 別記の方法で,8月12日(水)までにお申し込みください。
●吉野川の魚 吉野川には150種以上の魚が棲んでおり,種数の多さでは日本有数と言われています.そこにはどんな魚がどんな生活をしているのでしょうか.魚から見た吉野川とはどんな川なのかを探ります.
●中央構造線のはなし 中央構造線は、西南日本を地質構造のうえで内帯と外帯に分ける大きな断層です。また、四国や紀伊半島では、新しい時代にも活動したことのある活断層としてもよく知られています。徳島県下では池田から鳴門まで、阿讃山地の南麓に沿って東西にとおっています。この構造線の地質学的な位置づけ、活動の歴史、県下での断層露頭などについて紹介します。
○日 時 8月23日(日)午後1時30分〜午後4時
○場 所 脇町福祉センター(美馬郡脇町)
○講 師 佐藤 陽一(博物館主任学芸員)
両角 芳郎(博物館副館長)
○対 象 小学生から一般(小学生は保護者同伴)
○定 員 100名
※申し込みは必要ありません(直接会場へおこしください)。
夏休みに採集した生物や岩石などの標本で名前がわからないものを,講師の先生に教えてもらいながら名前を調べる会です.対象とするものは植物(コケ,キノコ,海藻を除く),昆虫や貝などの動物,岩石・鉱物・化石です.
★調べようとするものの準備:
(1)種類ごとにわけておく.
(2)まちがっていてもかまわないので,図鑑を使って自分で名前を調べてみる(図鑑は博物館のレファレンスルームにもあります).
(3)標本の数を一人30点以内にする.
(4)わからないところ,質問したいところをはっきりさせておく.
○日 時 8月26日(水)午前10時〜12時 午後1時〜4時
(受付:午前9時30分〜午後3時30分)
○場 所 博物館3階 実習・講座室
○対 象 小学生から一般 ※申し込みは必要ありません(直接会場へおこしください)。
往復はがきに 1. 希望行事名
2.参加希望者全員の氏名と住所(学生の場合は学年も)3.電話番号を記入し,行事予定日の1ヶ月前から10日前までに届くように下記までお申し込みください。返信用はがきの住所・氏名も忘れずに記入しておいてくだい。希望者が多数の場合は抽選します。なお,くわしいことは当選された方にお知らせします。
原則的に,参加費は無料です。
申込先 〒770 徳島市八万町向寺山 徳島県立博物館 普及係
TEL 0886-68-3636