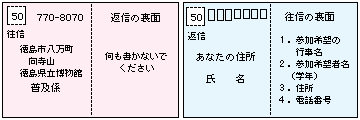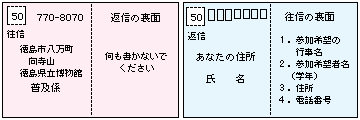
徳島県立博物館の催し物ご案内です.ふるってご参加ください.
化石に付着した砂岩や泥岩などを落とす作業をクリーニングといいます。標本の良し悪しを決定する大事な作業です。また,多少のテクニックと手先の器用さと根気が必要な,緊張感のある楽しい作業でもあります。
この行事でクリーニングを体験してみませんか。材料は,新生代第三紀鮮新世後期(約300万年前)の貝化石で,道具は普通に手に入るものだけで行います。
○日 時 10月4日(日)午後1時〜午後4時
○場 所 博物館3階 実習室
○講 師 中尾 賢一(博物館学芸員)
○対 象 小学生高学年から一般
○定 員 20名
○申込方法 別記の方法で,9月24日(木)までにお申し込みください。
サツマイモ,ジャガイモ,サトイモ,ヤマイモ,芋にはいろいろありますが,皆さん,カシュウという芋を食べたことがありますか?
この芋はヤマイモの一種で,かつては栽培されて普通に食べられていた芋です。けれども,現在の私たちの生活の中では,すっかり忘れさられています。 このカシュウ芋がどんな芋なのか,どのように使われていたのか,そしてどうして消え去っていったのかということについてお話します。
博物館で栽培したカシュウ芋の試食もしたいと思います。
○日 時 10月10日(土)午後2時〜午後3時
○場 所 博物館3階 講座室
○講 師 庄武 憲子(博物館学芸員)
○対 象 小学生から一般
○定 員 50名
※申し込みは必要ありません(直接会場へおこしください)。
古代の人びとは,みずから土をこねて土器を焼いていました。縄文土器は深いものが多く,これらはナベとして使われました。弥生土器は甕,壺,高坏と用途によって形がきまっており,機能的な美しさがあります。
自らの手で土器をつくり,古代の人びとの工夫のあとを体験してみましょう。
○日 時 10月11日(日)午後1時30分〜午後4時
○場 所 博物館3階 実習室
○講 師 高島 芳弘(博物館主任学芸員)
○対 象 小学生から一般(小学生は保護者同伴)
○定 員 36名
○申込方法 別記の方法で,10月1日(木)までにお申し込みください。11月15日(日)に行う土器づくり2(焼成)とセットです。両方参加できる人にかぎります。
今から約1,600〜1,400万年前に瀬戸内区に生まれた内海は,第一瀬戸内海とよばれています。この海に堆積した地層からは豊富な化石が産出しますが,ヒルギシジミやセンニンガイなどのマングローブ沼にすむ貝の化石も見つかっています。これらの地層や化石を調べることによって明らかになった第一瀬戸内海の変遷や,日本列島が熱帯〜亜熱帯性の環境だった証拠などについてお話ししていただきます。
○日 時 10月18日(日)午後1時30分〜午後3時
○場 所 21世紀館イベントホール
○講 師 糸魚川淳二氏(名古屋大学名誉教授)
○対 象 小学生から一般
○定 員 300名
※申し込みは必要ありません(直接会場へおこしください)。
○日 時 10月25日(日)午後2時〜午後3時
○場 所 博物館1階 企画展示室
○講 師 両角 芳郎(博物館副館長)
○対 象 小学生から一般
○定 員 50名
※申し込みは必要ありません(直接会場へおこしください)。
往復はがきに 1. 希望行事名
2.参加希望者全員の氏名と住所(学生の場合は学年も)3.電話番号を記入し,行事予定日の1ヶ月前から10日前までに届くように下記までお申し込みください。返信用はがきの住所・氏名も忘れずに記入しておいてくだい。希望者が多数の場合は抽選します。なお,くわしいことは当選された方にお知らせします。
原則的に,参加費は無料です。
申込先 〒770 徳島市八万町向寺山 徳島県立博物館 普及係
TEL 0886-68-3636