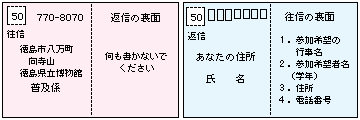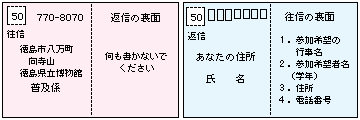
徳島県立博物館の催し物ご案内です.ふるってご参加ください.
○日 時 11月1日(日)午後2時〜午後3時
○場 所 博物館1階 企画展示室
○講 師 両角 芳郎(博物館副館長)
○対 象 小学生から一般
○定 員 50名
※申し込みは必要ありません(直接会場へおこしください)。
秋にはキクの花が咲きますが,那賀川周辺にはそこでしか見ることのできないナカガワノギクが生育しています。ナカガワノギク誕生の裏には,その名の通り那賀川の影響が隠されています。鷲敷周辺に分布するワジキギクもその秘密をとく鍵のひとつです。
今回はナカガワノギクを中心に,秋の那賀川の植物をバスに乗って探索してみます。
○日 時 11月8日(日)午前9時〜午後5時30分
○場 所 阿南市〜相生町までの那賀川沿い(貸切バスを利用)
○講 師 小川 誠(博物館主任学芸員)
○対 象 小学生から一般
○定 員 45名
○申込方法 別記の方法で,10月29日(木)までにお申し込みください。
海は私たちには計り知れない世界です。海の生きものの中から,代表的なものとして貝とカニとクラゲを取り上げ,それぞれについて,生活の仕方,習性,形などについてお話しします。貝についてはいくつか標本を出して,それに関連したこともお話しします。
○日 時 11月14日(土)午後2時〜午後3時
○場 所 博物館3階 講座室
○講 師 田辺 力(博物館主任学芸員)
○対 象 小学生から一般
○定 員 50名
※申し込みは必要ありません(直接会場へおこしください)。
○日 時 11月15日(日)午前10時〜午後3時
○場 所
○対 象 土器づくり1に参加した人
岩石も顕微鏡(偏光顕微鏡)で観察することができます。このためにつくられるのが岩石薄片です。岩石を光が通るような薄さ(30/1000mmほど)まで磨いたもので,岩石のつくりや中に入っている鉱物を調べるに欠かせません。
薄片は普通は特別な道具を使ってつくりますが,この行事では身の回りにあるものでつくってみます。岩石なんて光など全く通しそうにないと思われそうですが,うまくつくると,肉眼で見るのとはまったく別なもののように見えます。この行事で薄片づくりに挑戦してみませんか?材料の岩石は,特につくりやすく見ごたえのあるものを用意しています。
○日 時 11月22日(日)午後1時〜午後4時
○場 所 博物館3階 実習室
○講 師 中尾 賢一(博物館学芸員)
○対 象 小学校高学年から一般(小学生は保護者同伴)
○定 員 20名
○申込方法 別記の方法で,11月12日(木)までにお申し込みください。
「レプリカ」というのは,実物から特殊な方法で型どりをしてつくられた精密な複製品のことです。レプリカは「にせもの」とか「つくりもの」と思われがちですが,見た目には実物とほとんど区別がつかないほど精巧につくられていて,博物館などで展示資料としてはもちろん,資料保存のためにもたいへん役立っています。また立体的な記録の手段や,専門の研究者の研究資料としてもじゅうぶんに利用できるものなのです。
今回の実習では,実際にアンモナイトの化石などから型どりをしてレプリカをつくり,レプリカが持つ価値について知っていただこうと思います。
○日 時 11月29日(日)午後1時〜午後4時
○場 所 博物館3階 実習室
○講 師 魚島 純一(博物館学芸員)
○対 象 小学生から一般(小学生は保護者同伴)
○定 員 30名
○申込方法 別記の方法で,11月19日(木)までにお申し込みください。12月6日(日)に行うレプリカづくり2(色つけ)とセットです。
両方に参加できる人に限ります。小学生は保護者同伴で参加のこと。
11月19日までに届くように往復ハガキでお申し込みください。
往復はがきに 1. 希望行事名
2.参加希望者全員の氏名と住所(学生の場合は学年も)3.電話番号を記入し,行事予定日の1ヶ月前から10日前までに届くように下記までお申し込みください。返信用はがきの住所・氏名も忘れずに記入しておいてくだい。希望者が多数の場合は抽選します。なお,くわしいことは当選された方にお知らせします。
原則的に,参加費は無料です。
申込先 〒770 徳島市八万町向寺山 徳島県立博物館 普及係
TEL 0886-68-3636