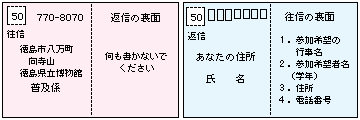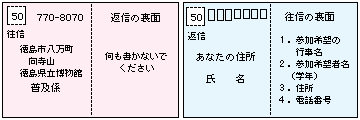
徳島県立博物館の催し物ご案内です.ふるってご参加ください.
縄文時代になって,人びとは竪穴式住居をつくり,一定の場所に住むようになりました。時には数十軒の規模のムラを形づくることもありました。
縄文時代の初めには,竪穴住居跡よりも岩蔭遺跡がよく知られています。岩蔭での居住の形態がどのようであったのかも興味をひかれるところです。最近になって鹿児島県の上野原遺跡などで大きなムラが発見され,定住の歴史がいつまでさかのぼるのか議論がわき起こっています。どのような生業がこれらのムラを支えていたのかも含めて,定住の歴史をたどってみたいと思います。
○日 時 1月9日(土)午後2時〜午後3時
○場 所 博物館3階 講座室
○講 師 高島 芳弘(博物館主任学芸員)
○対 象 小学生から一般(小学生は保護者同伴)
○定 員 50名
※申し込みは必要ありません(直接会場へおこしください)。
徳島県は多くの川に恵まれています。人々は川とどのようにつき合って暮らしてきたのでしょうか。ここでは,主に聞き取りによって得られた伝承をもとに,人と川の関係について3回シリーズで振り返ってみたいと思います。
1回目は,県内で伝えられてきた水にすむ妖怪・河童の昔話の特徴から,河川流域の人々が水とどのようなつきあい方をしてきたかを考えます。
2回目は,河川流域の植生の変遷から水辺の環境の変化について,3回目は,川辺で生活をしてきた人の話から,川とのつき合いの変化について考えたいと思います。
○日 時 1月23日(土)午後2時〜午後3時30分
○場 所 博物館3階 講座室
○講 師 庄武 憲子(博物館学芸員)1.3回
鎌田 磨人(徳島大学助教授)2回
○対 象 小学生から一般(小学生は保護者同伴)
○定 員 50名
○申込方法 別記の方法で,1月13日(水)までにお申し込みください。3回(1月23日・2月27日・3月27日)連続出席可能者。
落ち葉をもってきて,それを顕微鏡でぐっと拡大してみると,そこは,おもしろい形や色をした生きものたちでいっぱいのおとぎの国です。落ち葉のジャングルの中を,しっぽにジャンプ用のバネをもつトビムシ,カブトムシのようなよろいをもつササラダニ,そしてサソリのようなカニムシなどが歩いていきます。これはぜひ自分の目でみて体験してください。観察では,自分で落ち葉を採ってきて,その中の生き物を生きたまま顕微鏡で見ることも行います。
○日 時 1月24日(日)午後2時〜午後4時
○場 所 博物館3階 実習室
○講 師 田辺 力(博物館主任学芸員)
○対 象 小学生から一般(小学生は保護者同伴)
○定 員 40名
○申込方法 別記の方法で,1月14日(木)までにお申し込みください。
往復はがきに 1. 希望行事名
2.参加希望者全員の氏名と住所(学生の場合は学年も)3.電話番号を記入し,行事予定日の1ヶ月前から10日前までに届くように下記までお申し込みください。返信用はがきの住所・氏名も忘れずに記入しておいてくだい。希望者が多数の場合は抽選します。なお,くわしいことは当選された方にお知らせします。
原則的に,参加費は無料です。
申込先 〒770 徳島市八万町向寺山 徳島県立博物館 普及係
TEL 0886-68-3636