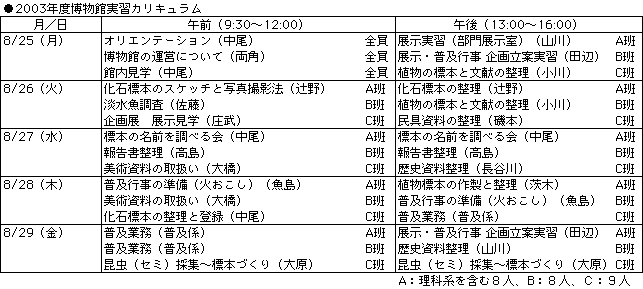|
普及教育事業、とくに普及行事は、「開かれた博物館」をめざし、館員が県民と直接交流できるよい機会であり、力点をおいて取り組んでいる。
平成15年度は、年間71回の普及行事を実施した(実施計画では76回、雨天などでの中止5回。他にクイズラリー24回を行った)。普及行事は県民のあいだに定着してきてはいるが、参加者は徳島市内とその近郊在住者に片寄っている。そのため、歴史散歩、野外自然かんさつ、移動講座において、郡部での開催を増やすなどの工夫をしているが、徳島市以外での行事に対しても参加者は徳島市、鳴門市、小松島市、及び名西郡石井町等からの参加者が多い。今後、広報の方法などにもさらに工夫が必要であると考えている。
1.普及行事
■歴史体験
昔の人々の生活に関係のある体験を通じて、ものの性質や当時の人々の生活の知恵を学ぶシリーズ。
4月19日(日)石ヤリをつくろう 参加者 41人
6月15日(日)土器文様の作り方 6人
6月22日(日)勾玉をつくろう 48人
7月19日(土)火おこし[1] 47人
8月3日(日)火おこし[2] 33人
8月16日(土)戦時中の食事・すいとんをつくろう 28人
11月16日(日)石のナイフで切ってみよう 20人
12月7日(日)ベーゴマをまわしてみよう 24人
1月25日(日)七輪で鍛冶屋さん 25人
■歴史散歩
県内の主な遺跡、町並み、建造物などを見学してまわるシリーズ。
5月25日(日)古墳見学[1] 42人
10月5日(日)石造物をさがそう 21人
11月23日(日)万年山を歩こう 22人
12月14日(日)古墳見学[2] 20人
1月18日(日)一宮城を歩こう 35人
3月21日(日)古墳見学[3] 36人
3月28日(日)池田を歩こう 22人
■野外自然かんさつ
野外にでかけて行う季節に応じた動植物の観察や地質の見学会。15年度は文化の森周辺のほか、徳島市、鳴門市、引田町、勝浦川河口、那賀川町、羽ノ浦町、由岐町、などで実施した。
5月4日(日)眉山の地質見学 28人
5月18日(日)磯のいきもの[1] 64人
6月1日(日) 磯の生き物[2] 中止
7月13日(日)川魚かんさつ 41人
7月27日(日)漂着物を探そう! 24人
8月2日(土)水生昆虫の観察 53人
9月6日(土)鳴く虫のかんさつ 47人
9月28日(日)河口のいきもの 29人
10月12日(日)アサギマダラをさがそう 中止
11月2日(日)鉱物さがし 22人
■室内実習
主に実習室で行う各種の観察会、講習会。内容に応じて実体顕微鏡、電子顕微鏡、蛍光X線分析装置、赤外線テレビカメラ等の機器も併用して観察を行っている。
「標本の名前を調べる会」は、毎年8月下旬に行う恒例の行事で、学芸員のほか8名の外部講師の応援を得て実施した。単に名前を教えるだけにならないで、いっしょに調べる姿勢で取り組むよう留意している。
4月27日(日)春の植物かんさつ 17人
5月25日(日)ミクロの世界−電子顕微鏡で昆虫を見よう[1] 33人
6月8日(日)ミクロの世界−電子顕微鏡で化石を見よう[1] 22人
8月2日(土)植物標本の作り方・名前の調べ方 11人
8月10日(日)かんたんな貝の標本の作り方 25人
8月27日(水)標本の名前を調べる会 250人
9月7日(日)ミクロの世界−電子顕微鏡で植物を見よう[1] 27人
9月14日(土)こどもレプリカ教室 46人
10月19日(日)秋の植物観察−花のつくりをしらべよう− 8人
12月6日(土)ミクロの世界−電子顕微鏡で化石を見よう[2] 14人
1月18日(日)落ち葉の中のいきものたち[1] 23人
2月 8日(日)貝化石標本の作り方 22人
2月15日(日)ミクロの世界−電子顕微鏡で植物を見よう[2] 25人
2月 29日(日)落ち葉の中のいきものたち[2] 31人
3月7日(日)ミクロの世界−電子顕微鏡で昆虫をみよう[2] 40人
■みどりの探検隊
4月20日(日)春の吉野川に咲く植物を探そう 中止
5月11日(日)春の渓谷に咲く花を探そう 中止
8月10日(日)夏の吉野川に咲く花を探そう 中止
10月5日(日)秋の吉野川に咲く花を探そう 8人
10月26日(日)秋の渓谷に咲く花を探そう 11人
■みどりの工作隊
自然の材料を使い、遊びの要素を取り入れた実習。
7月20日(日)押し葉カルタであそぼう 24人
8月24日(日)葉脈標本できれいなしおりを作ろう 33人
11月3日(月)ドングリゴマを回そう 131人
11月30日(日)雑草や木で年賀状を作ろう 28人
2月22日(日)竹であそぼう 33人
■ミュージアムトーク
土曜日の午後に、学芸員が各自の研究テーマや身近な話題について話をするシリーズ。申し込み不要・定員先着50名で実施している。
4月26日(土)歴史を決めた戦い 22人
6月7日(土)民具と地域−カラサオ− 2人
7月26日(土)やさしい地層と化石のはなし 21人
9月20日(土) 阿波の中世文書−その謎をさぐる− 14人
1月17日(土)お地蔵さんの仏像 17人
3月13日(土)美しいアンモナイトのはなし 8人
■移動講座
移動博物館の試みとして、学芸員が講師をつとめて館外の社会教育施設と共催で行う講座。15年度は11〜12月に阿波海南文化村で実施した。
11月9日(日)文芸に見る阿波の中世[1] 13人
12月7日(日)文芸に見る阿波の中世[2] 24人
■企画展関連行事
企画展開催中に、次の講演会、展示解説等の行事を行った。
●企画展「歴史を決めた戦い」記念講演会
5月11日(日)
会 場:21世紀館イベントホール
講 師:西ケ谷恭弘(日本城郭史学会代表)
演 題:鉄砲と長篠合戦
参加者:140人
●企画展「歴史を決めた戦い」展示解説
第1回:4月27日(日) 参加者 51人
. 第2回:5月18日(日) 参加者 41人
●アイヌ文化フェスティバル講演会
7月19日(土)
会 場:21世紀館イベントホール
講 師:丸山隆司(藤女子大学文学部教授)
演 題:知里幸恵の<言語>
参加者:212人
●アイヌ文化フェスティバル芸能公演
7月19日(土)
会 場:21世紀館野外劇場
公 演:ムックリ演奏とアイヌ古式舞踊、口承文芸、アイヌ民族音楽演奏ほか
参加者:727人
●企画展「アイヌからのメッセージ―ものづくりと心―」記念講演会
7月21日(月)
会 場:21世紀館イベントホール
講 師:大塚和義(国立民族学博物館教授)
演 題:鳥居龍蔵とアイヌ文化
参加者:104人
●企画展「アイヌからのメッセージ―ものづくりと心―」展示解説
第1回:7月20日(日) 参加者34人
第2回:8月10日(日) 参加者35人
●企画展「アイヌからのメッセージ―ものづくりと心―」関連体験学習(博物館実習室)
[1]アイヌの楽器ムックリをつくろう
7月27日(日) 参加者 99人
[2]アイヌ文様を彫ってコースターをつくろう
8月17日(日) 参加者 67人
●企画展「アンモナイトのすべて」記念講演会
11月9日(日)
会 場:21世紀館イベントホール
講 師:岡本 隆(愛媛大学理学部助教授)
演 題:アンモナイトを復元する
参加者:110人
●企画展「アンモナイトのすべて」展示解説
第1回:10月26日(日) 参加者 50人
第2回:11月16日(日) 参加者 45人
■クイズラリー
毎月第2・第4土曜日(祝日を除く)に、小・中・高校生を対象にクイズラリーを実施している。この行事は、常設展の活用と入館者の獲得を目的に始めたもので、参加者が展示資料に関する簡単な問題を解きながら観覧することで、新しい発見につながることを期待している。参加者全員に簡単な記念品を贈呈している。
4月12日(土) 105人(小 101・中 4・高 0)
4月26日(土) 117人(小 112・中 5・高 0)
5月10日(土) 113人(小 108・中 4・高 1)
5月24日(土) 138人(小 123・中 12・高 3)
6月14日(土) 122人(小 116・中 6・高 0)
6月28日(土) 126人(小 116・中 10・高 0)
7月12日(土) 94人(小 91・中 3・高 0)
7月26日(土) 101人(小 90・中 11・高 0)
8月9日(土) 113人(小 101・中 12・高 0)
8月23日(土) 108人(小 92・中 16・高 0)
9月13日(土) 133人(小 127・中 5・高 1)
9月27日(土) 160人(小 152・中 7・高 1)
10月11日(土) 143人(小 138・中 5・高 0)
10月25日(土) 116人(小 109・中 5・高 2)
11月8日(土) 152人(小 146・中 6・高 0)
11月22日(土) 121人(小 118・中 3・高 0)
12月13日(土) 122人(小 121・中 1・高 0)
12月27日(土) 68人(小 68・中 0・高 0)
1月10日(土) 105人(小 103・中 2・高 0)
1月24日(土) 93人(小 89・中 3・高 1)
2月14日(土) 75人(小 75・中 0・高 0)
2月28日(土) 104人(小 103・中 1・高 0)
3月13日(土) 125人(小 121・中 4・高 0 )
3月27日(土) 110人(小 109・中 1・高 0)
参加者合計 2,764人(小2,629・中126・高9)
■その他の普及行事
●博物館こどもの日フェスティバル
5月5日(月)
博物館と友の会の共催でウォークラリーを実施した。文化の森に10のチェックポイントを設置し、それぞれの問題を解きながら各施設をめぐる。小学生以下の子どもたちには記念品を贈呈した。
参加者:1,025人
2.講師派遣、テレビ・ラジオへの出演等
館外からの依頼を受けて行った講師派遣、テレビ・ラジオへの出演等を、月日・担当者・内容(依頼者)の順に記す(内容に依頼者が表現されている場合は依頼者を省略)。これらも広義の普及教育活動につながるとの観点から、業務に支障のない限り依頼を受け入れることにしている。
4月8日 茨木 靖 NHKテレビ「情報交差点とくしま−カルチャーアンドネイチャー」出演(サキシマ スオウノキとモモタマナ)
7月24日 魚島純一 徳島県立文書館古文書保存講座で講演「文書資料の保存科学」
8月30日 魚島純一 四国放送ラジオ「JRTラジオまつり 遊びの広場」出演(ベーゴマ指導担当)
9月2日 両角芳郎 NHKテレビ「情報交差点とくしま−カルチャーアンドネイチャー」出演(アンモナイトのいろいろ)
9月5日 茨木 靖 四国放送テレビ「おはよう徳島」 阿部近一氏の寄贈資料の紹介
9月7日 長谷川賢二 平成15年度北近江歴史大学で講演「修験道―伊吹山と山岳信仰―」(滋賀県山東町ルッチ・プラザ)
9月20日 山川浩實 NHK「武蔵」テレビセミナーで講演「合戦とサムライ−関ヶ原の戦いと蜂須賀氏」
9月12日 長谷川賢二 第2回徳島県隣保館関係職員研修会「トーク&トーク 部落差別の現実とその根源を問う」パネラー(国民宿舎津乃峰荘)
9月18日 長谷川賢二 人権保育係保育士研修会で講演「部落差別と迷信・ケガレ観念のあいだ」(徳島市保険福祉部)
10月8日 大橋俊雄 第23回徳島県シルバー大学校穴吹校講義「弘法大師のもたらした仏像」
11月18日 大橋俊雄 第23回徳島県シルバー大学校三加茂校講義「弘法大師のもたらした仏像」
10月20日 大橋俊雄 第23回徳島県シルバー大学校鳴門校講義「弘法大師のもたらした仏像」
12月4日 大橋俊雄 第23回徳島県シルバー大学校穴吹校講義「弘法大師のもたらした仏像」
12月6日 山川浩實 徳島城址を愛する会第3回セミナーで講演「徳島城の構えとその特徴について」
1月13日 大橋俊雄 第23回徳島県シルバー大学校小松島校講義「弘法大師のもたらした仏像」
1月27日 長谷川賢二 平成15年度徳島市文化財保勝会連絡協議会文化財研修会で講演「中世の熊野信仰と阿波」(昴宿よしの)
1月30日 大橋俊雄 第23回徳島県シルバー大学校徳島校講義「弘法大師のもたらした仏像」
2月25日 茨木 靖 NHKテレビ「情報交差点とくしまNature and
culture」出演(飛ぶ種)
3.博物館実習生の受け入れ
博物館実習は、博物館法施行規則第1条で、学芸員となる資格を取得するために「大学において修得すべ
き博物館に関する科目」と規定されているもののひとつで、登録博物館または博物館相当施設における実習で修得することになっている。
当館では、大学からの依頼により原則として県出身の学生を受け入れることにし、夏休み期間中に実習を行っている。4月1日〜5月15日が受付期間で、希望者が多い場合は調整を行い、20数名をめどに承諾書を発行することにしている。
平成15年度は、8月25〜29日に実習生の受け入れを行った。実習生は25人(男8人、女17人)で、大学別の内訳は次のとおりである。
徳島大学 3人 法政大学 1人
神戸学院大学 1人 京都女子大学 2人
四国大学 10人 高知女子大学 1人
徳島文理大学 2人 鳴門教育大学 2人
東海大学 1人 奈良女子大学 1人
金沢大学 1人
カリキュラムは別表のとおりである。学芸員と普及係職員が指導にあたり、資料の整理や調査などについての実習を行った。
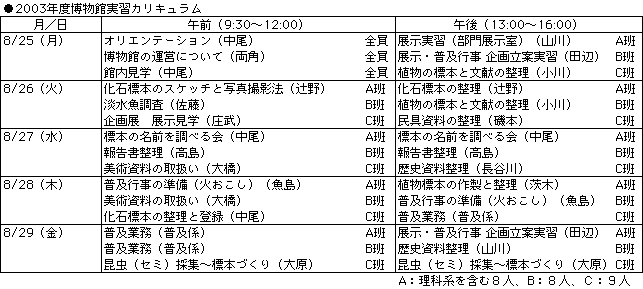
4.学校教育との連携
博物館ではこれまでにも、学校行事(遠足等)での団体見学の受け入れや児童・生徒向けの各種普及行事などを行ってきた。しかし、最近の教育改革に伴う学校完全週5日制や「総合学習」の導入、社会人講師の受入れ等々と関連し、博物館等の社会教育機関に対してもっと積極的な学校教育への支援が要請されるようになってきた。
博物館は本来、実物資料に基づく体験的な学習ができる場であり、学校教育にとって役立つところであるはずである。当館としても博物館のもつ資源(もの・情報・人)とその活用法を普及するとともに、意識的・系統的に学校教育を支援する活動を行っていくことにしている。
平成12・13年度には「博物館と学校との連携に関する研究会」(略称「博学連携研究会」)を組織し、博物館と学校との連携のあり方等についての協議を行ってきた。それを踏まえて、14年度は各支援を発展させ、成果を教育利用説明会で発表した。また、平成15年度は、教職員向けの博物館利用リーフレットを作成した。
(1)学校の授業での博物館利用への支援
理科や社会科の授業、「総合学習」での活動と関連して、クラスやグループ単位で博物館を利用する例が増えてきた。受け入れに当たっては、展示資料だけでなく必要に応じて収蔵資料を見てもらったり、学芸員が助言するなどの支援を行った。
[1]鴨島養護学校(鴨島町)16人
5月15日(木)
企画展「歴史を決めた戦い」の展示説明を日本史の授業の一環として、学芸員が説明を行った。(担当者:山川)
[2]板野南小学校(板野町)3年生・35人
6月27日(金)
「博物館へ行こう」の授業として来館。学芸員が博物館の裏側を案内。(担当者:大原)
[3]上八万小学校(徳島市)4年生・72人
10月15日(水)
総合学習「太鼓づくり」で来館。常設展を見学後、講座室で太鼓の歴史や、徳島における太鼓づくりについて講話を行った。(担当者:長谷川)
[4]久勝小学校(阿波町)6年生・30人
10月31日(金)
特別授業「化石のはなし」で常設展・企画展の観覧を兼ねて来館。所蔵資料を臨時に実習室へ陳列し、学芸員が説明しながら化石についての授業を行った。(担当者:中尾)
[5]八万南小学校(徳島市)3年生
10月31日(金)125名;11月18日(火)44名
総合学習(調べ学習)で来館。1日目に博物館の展示や文化の森各施設を見学し各々が課題を設定した。その中で博物館について課題をもっている児童が2日目再来館。それぞれの課題について学芸員が説明後、博物館の裏側見学も行った。(担当者:両角・ 中尾・庄武・佐藤・茨木・大原)
[6]福島小学校(徳島市)3年生・80名
11月7日(金)
「むかしの道具調べ」て来館。民具の観察とスケッチを行った。(担当者:磯本・古東)
[7]上八万小学校(徳島市)4年生・120名
11月14日(金)
総合学習のテーマとしてとくしま空襲を講座室で説明。その後常設展を見学した。(担当者:山川)
[8]早稲田実業学校(東京都)高等部2年生・5人
12月9日(火)
校外教室(地域調査)「徳島の文化」で来館。(担当者:大橋)
(2)学校の授業への講師派遣(出前授業)
学校からの依頼に応じて、学校での授業に学芸員を派遣した。授業では教員と協同し、持参した博物館資料を活用するなどして、児童・生徒の理解を助けるよう工夫した。
[1]大松小学校(徳島市) 4月30日(水)
6年生2クラスで社会科の学習「火おこし」の授業を、博物館から持参した火おこしの道具を使って教員と協同して行った。(講師:魚島)
[2]八万南小学校(徳島市)5月7日(水)・8日(木)
6年生3クラスで社会科の学習「火おこし」の授業を、博物館から持参した火おこしの道具を使って教員と協同して行った。(講師:魚島)
[3]板野南小学校(板野町) 5月28日(水)
3年生35名に昆虫の体のつくりを説明し、世界の代表的な昆虫の標本を見ながら、昆虫の紹介を行った。(講師:大原)
[4]上八万小学校(徳島市) 7月11日(金)
5年生83名に学校の近くを流れる園瀬川の水生昆虫の採集と観察を行った。(講師:大原)
[5]国府小学校(徳島市) 6月23日(月)
全校生徒を対象にして、総合学習で用水路の魚類生息調査を行った。(講師:佐藤)
[6]宮井小学校(徳島市)7月1日(火)
5-6年生が、総合学習のテーマとしてホタルの生息できる環境について研究を行っており、当日研究授業が行われた.その発表会の後、参加した理科担当の教員約40名にホタルについての一般的な説明を行い、宮井小学校周辺の水系の環境とホタルの生息の可能性について話した。(講師:大原)
[7]八万南小学校(徳島市)7月9日(水)
4年生127名を対象に、文化の森総合公園下の園瀬川で水生昆虫の採集と観察を行った(講師:大原)
[8]助任小学校(徳島市) 9月22日(月)
3年生138名に、総合的な学習での「吉野川」の一環として、「吉野川の生き物について」授業を行った。(講師:佐藤)
[9]国府養護学校(徳島市)10月1日(水)
高校3年生8名を対象に土器づくりのうち形をつくることだけを行った。(講師:高島)
[10]国府養護学校(徳島市)10月8日(水)
文様の道具のつくりかたや使い方の説明をしながら、前回形をつくった土器に、実際に文様をつけてもらった。(講師:高島)
[11]城東高等学校(徳島市)10月9日(木)
1年生の総合学習「職業ガイダンス」において、人文科学グループ9名に対し、学芸員の仕事について話した。(講師:長谷川)
[12]山口小学校(阿南市) 10月21日(火)
6年生10名を対象に地層と化石についての授業を行った。(講師:中尾)
[13]城西高等学校(徳島市) 10月31日(金)
3年生20名を対象に中生代の化石についての授業を行った。(講師:辻野)
[14]上八万小学校(徳島市) 11月4日(火)
4年生83名を対象に園瀬川の魚の観察を行った。(講師:佐藤)
[15]芝生小学校他(三野町) 11月5日(水)
6年生64名を対象に地層のでき方や中央構造線についての授業を行った。(講師:辻野)
[16]木頭小学校 (木頭村) 11月13日(木)
6年生8名を対象に地層と化石についての授業を行った。(講師:辻野)
[17]栃之瀬小学校(東祖谷山村) 11月25日(火)
1、2年生7名を対象に「いろいろなタネと実」の授業を行った。(講師:茨木)
[18]栃之瀬小学校(東祖谷山村) 11月25日(火)
3、4年生13名を対象に「民具調べ」の授業を行った。(講師:磯本)
[19]山口小学校(阿南市) 1月15日(木)
6年生1クラスで総合的学習として調べ学習をし 授業参観で発表をした「銅鐸」についての出前授業を行った。学校では、出前授業を受けて、さらに現地調査などを含む調べ学習を追加し、再度発表する機会を設けた結果、児童の学習意欲を高めることに成功した。(講師:魚島)
(3)博物館資料の学校への貸出し
学校の授業等で活用してもらうため、平成10年度から博物館資料の学校への貸出しを行っている。学校貸出用資料リストを学校に配布して利用を呼びかけているが、まだ利用は少ない。
貸出用資料の一層の利用促進を図るため、昨年度末に学校貸出用資料解説シートを印刷し、今年度小中学校および高校に配布した。また、来館した教職員には必要に応じて解説シートを配布し利用を勧めた。
[1]富岡小学校(阿南市)5月10日
貸出資料:めだか模型
利用目的:理科の授業で利用
[2]富岡小学校(阿南市) 10月10日〜10月15日
貸出資料:化石標本28点
利用目的:児童の理科学習で利用
[3]上勝中学校(上勝町) 6月8日〜6月18日
貸出資料:火おこし道具・武具セット
利用目的:社会科の授業で利用
[4]上勝中学校(上勝町) 6月29日〜7月8日
貸出資料:復元青銅器・トロトロ石器等
利用目的:社会科の授業で利用
[5]川島高等学校(川島町) 6月14日〜6月29日
貸出資料:火おこし道具
利用目的:学校教育の一環で利用
[6]栃之瀬小学校(東祖谷山村)7月24日〜8月1日
貸出資料:火おこし道具
利用目的:学校教育の一環で利用
[7]川内中学校(徳島市) 9月13日〜9月30日
貸出資料:徳島大空襲資料
利用目的:社会科ならびに総合学習の時間に利用。
[8]岩脇小学校(羽ノ浦町)
貸出資料:徳島空襲パネル他
利用目的:総合的な学習
[9]上八万小学校(徳島市)
貸出資料:徳島空襲パネル他
利用目的:総合的な学習
(4)職場体験の受け入れ
中学校・高校での職場体験事業の受け入れを行い、生徒に博物館業務を体験してもらうことによって、博物館に対する認識を高めることができた。
[1]八万中学校(徳島市) 8月26日〜27日
3名 総合学習の一環として実施。
[2]阿波高校(阿波郡) 9月10日〜12日
1名 県インターンシップ推進事業
(5)教員のための研修
徳島県教育委員会等からの依頼により、教員対象の研修会を当館で実施し、当館職員が指導に当たった。
[1]名西郡小学校理科部会研修会
7月28日(月)レプリカづくり実習 参加者11名(講師:魚島)
[2]県内公立小学校教員「やさしい理科実験・観察講座」
7月30日(水)文化の森周辺の植物 参加者24名(講師:茨木)
[3]徳島県高等学校教育研究会理科部会地学部
11月19日(水)貝化石標本の作り方 参加者15名(講師:中尾)
[4]平成15年度10年経験者研修
7月23日(水) 参加者19名
古代の乳製品「蘇」をつくろう (講師:長谷川)
落ち葉の中のいきもの(講師:田辺)
8月1日(金) 参加者18名
勾玉をつくろう (講師:魚島)
川魚の採集と観察 (講師:佐藤)
8月8日(金) 参加予定者18名
土器づくり (講師:高島)(悪天候のため中止)
[5]徳島市小学校教育研究会総合部会
10月16日(木) 参加予定者18名
「石のナイフで切ってみよう」(講師:高島)
(6)その他
博物館での授業、講師派遣、資料の貸出しに限らず、学校の授業やクラブ活動等で自然観察、生活体験、歴史学習等をしようとする場合、どんなことをしたらおもしろいか、どんな資料が活用できるかなどについて、学芸員が博物館での普及行事等の経験を踏まえて教員の相談に応じることにしている。
[1]京都市理科研究会
5月24日(土)
徳島県内で行う地学系巡検についての情報提供(対応:中尾)
[2]徳島市立高校理数科1年生(3名)と引率教員1名
3月31日(火)
微化石の観察方法と研究の進め方(対応:中尾)
5.博物館の広報活動
博物館ニュースをはじめ、企画展ポスター、年間催し物案内リーフレット、月間催し物案内等を定期的に幅広く配布することにより、博物館活動のPRにつとめている。これらは県庁記者クラブを通じて広報するほか、報道機関やタウン紙編集室などへも直送している。また、必要に応じて報道機関への資料提供を行っている。さらに、電子メールを利用した催し物案内サービスも行った。
●博物館ニュース、ポスター等の主な県内定期発送先
小学校 241ケ所
中学校 92
高等学校・その他学校 59
学会・研究所・同好会等 100
県および県教育委員会各課・機関 66
市町村教育委員会 50
公民館・隣保館 228
市町村および大学図書館 33
博物館施設 435
宿泊施設 38
報道関係機関等 72
●電子メールサービス
登録者 430人(平成16年3月31日現在)
●報道機関への資料提供
毎月の催し物案内・県庁だよりへの掲載や、美術品等取得基金によって3月末、8月末に購入した資料の内容についても資料提供を行った。
4月2日 県立博物館の購入資料について
4月9日 企画展「歴史を決めた戦い―信長の台頭から 家康の覇権まで―」の開催について
6月18日 部門展示「巡礼の世界」の開催について
8月15日 国広作 刀・脇指の寄贈について
8月25日 部門展示「徳島城と天守閣」の開催について
8月29日 「とくしまミュージアムスタンプラリー」の実施について
9月5日 県立博物館の購入資料について
9月20日 企画展「アンモナイトのすべて」の開催について
12月19日 常設展特設コーナー「申(さる)」の展示について
1月23日 特別陳列「日本刀の美―赤羽刀とその他の 館蔵品」の開催について
1月23日 部門展示「楠氏寄贈の美術品」の開催について
2月6日 常設展特設コーナー「牟岐大島の自然とくらし」の展示について
3月2日 部門展示「復元青銅器」の開催について
6. 博物館友の会
●会員(平成15年度末)
個人会員(年会費 2,000円) 106 人
家族会員(年会費 3,000円) 84組・312人
賛助会員(年会費 10,000円) 1 人
●役員(平成15年度)
会 長:行成正昭
副会長:和田賢次・関眞由子・両角芳郎(博物館長)
幹 事:石原 侑・徳山 豊・多田精介・樫原剛一・南部洋子・木下 覚・澤祥二朗・大杉洋子・石尾和仁
監 査:森本康滋・川下浩子
●事業
[1]博物館出版物の増刷・頒布
博物館発行の企画展図録および解説書の増刷・頒布を行った。
[2]広報活動
15年度会員に対し、博物館ニュース、企画展チラシ、月間行事案内、年間催し物案内などを送付した。また、友の会会報「アワーミュージアム」No.22〜24を発行し、会員に送付した。
[2]企画展説明会
企画展「歴史を決めた戦い」、「アイヌ工芸品展」、及び「アンモナイトのすべて」の開催期間中に、会員を対象とした説明会を行った。
[3]野外活動等
会員を対象とした行事を8回実施した。
○こどもの日フェスティバル(博物館と共催)
文化の森全体を使ってウォークラリーを実施した。近代美術館や文書館の協力も得て10のチェックポイントをめぐった。参加した小学生以下の子どもたちには記念品を進呈した。
日 時:5月5日(月)9:30〜16:00
場 所:文化の森総合公園及び各施設
参加者:1025人
○第10回 園瀬川探検
日 時:6月8日(日)9:00〜15:00
場 所:佐那河内村
参加者:6人
○自然体験「田植え」、「稲刈り」
日 時:6月28日(土)、10月25日(土)
場 所:八万町
参加者:7人(のべ14人)
○秋の研修会 「しまなみ海道美術館探訪」
日 時:9月7日(日)7:10〜18:15
場 所:愛媛県大三島方面
参加者:42人
○第11回 園瀬川探検
日 時:10月26日(日)9:00〜15:00
場 所:佐那河内村
参加者:5人
○冬の研修会「晩秋の土佐路を訪ねて」
日 時:11月22日(土)〜23日(日)
場 所:高知県越知町・室戸市方面
参加者:24人
○落ち葉の中の生き物special
日 時:2月1日(日)
場 所:博物館実習室
参加者:12人
7. 普及教育関係出版物
■博物館見学ノート
2001年11月3日第3版発行、B5判56ページ
小・中学校の児童・生徒が博物館の展示を利用するにあたり、その教育効果を高めるのに役立つように作成されたワークシート形式のテキスト。
利用方法は多様であるが、主に遠足等で来館しワークシートでの学習を行う学校に配布している。
■博物館ニュース
館の広報誌で、内容は、学芸員の研究の一端を紹介する"Culture
Club"、館蔵品紹介、野外博物館、企画展案内、情報ボックス、レファレンスQ&A、普及行事の案内と記録などから構成されている。A4判・8ページ(全ページカラー)で6,000部を印刷している。
平成15年度には次の4号を発行した。また、当館ホームページでも公開している。
●No.51(2003年6月15日発行)
Culture Club 辰砂の精製
企画展 アイヌ工芸品展 アイヌからのメッセージ−ものづくりと心−
館蔵品紹介 八貫渡銅鐸
情報ボックス 南の島からやってきた木の実
友の会活動紹介 園瀬川探検
●No.52(2003年9月16日発行)
Culture Club 生きた化石 オウムガイ
館蔵品紹介 世界のコガネムシ科ほか甲虫類標本―石田正明コレクション―
企画展 アンモナイトのすべて
歴史散歩 戦争のモニュメント
レファレンスQ&A 「蘇民将来」のお札ってどんなものですか?
●No.53(2003年12月1日発行)
Culture Club 川環境と魚―FPOMの影響―
館蔵品紹介1 徳島市眉山の鉱物
館蔵品紹介2 森祖仙筆猿図 佐野山陰賛
情報ボックス 火打ち石―忘れ去られた徳島県の名産品―
レファレンスQ&A 秋の七草が減っているのは本当ですか?
●No.54(2004年3月25日発行)
Culture Club 正月のまつり方
情報ボックス 博物館に寄贈されたリビコセラスのホロタイプ
企画展 サメの世界
野外博物館 洞窟の生きものたち
レファレンスQ&A 徳島城の石垣の積み石には、どのような刻印がありますか?
■その他
●博物館催し物案内
1年間の普及行事予定を掲載したB4判4つ折のリーフレット。14万部印刷し、県内の小・中・高校生 及び教職員全員に配布した。また、博物館ニュースとともに発送するほか、展示室入り口に置いて来館者に自由にとってもらったり、普及行事の参加者に配布したりしている。
●月間催し物案内
各月の普及行事の実施要領、申し込み方法等の案内を印刷したB4のビラ。報道関係機関等に配布するほか、来館者にも提供している。
●博物館引率の手引き
学校の遠足などの利用に役立つよう、博物館の入館案内、見学に当たっての留意点、観覧料減免申請手 続きなどについて説明した印刷物。年度初めに県内各学校に送付している。
●博物館の学校支援事業案内
博物館が行っている学校への支援事業を、内容別に紹介したパンフレットを作製し、各学校へ送付した。
|