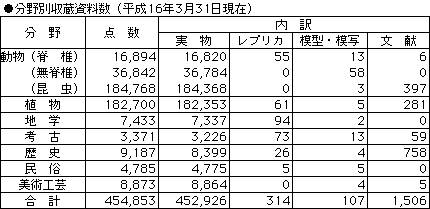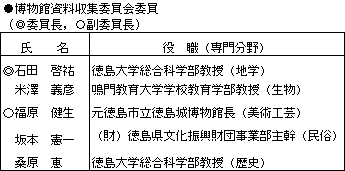|
資料の収集と保存は、博物館にとって最も基本的な機能である。当館では開館以来次の4つを基本方針として資料を収集している。
1)徳島の自然と人文に関する資料のすべてを収集の対象とする。
2)地域に根ざしたテーマを設定し,計画的かつ集中的な収集をする。
3)徳島の概要あるいは特性を把握するため,世界を対象とした比較資料の収集をめざす。
4)一次資料のみならず、すべての二次資料をも収集する。
資料の収集手段としては、採集・購入・寄贈・交換など様々な方法で行っている。学芸員自らが積極的に収集しているほか、最近では、県民や官公庁からの資料の寄贈も増えてきている。また、資料の購入には美術品等取得基金を充てている。
収集した資料は、調査研究に役立てているだけでなく、展示や教育活動、他の博物館や研究者への貸し出しなどを通じて有効に活用している。
平成15年度も5名(人文2、自然3)の文化推進員・臨時補助員の補助を得て、資料の整理作業を進めた。
1.採集資料
●動物
シマヘビ 1点
ハツカネズミ 1点
鴨島町三谷川産魚類 24点
カムルチー稚魚 2点
イノシシ幼獣 1点
那賀川産カジカ・アユカケ 多数
カジカガエル 1点
愛媛県鴨川産魚類 多数
ハリセンボン 1点
日本産多足類 多数
ドブガイ 4点
トガリアメンボほか水生半翅類標本 多数
マレーゼトラップによる県内産昆虫 20,000頭
●植物
県内各地の標本 多数
●地学
愛媛県土居町関川産岩石・鉱物 3点
高知県産鮮新世貝化石 多数
長崎県産更新世貝化石 多数
高知県産第三紀生痕化石 10点
和泉層群産白亜紀後期化石 5点
●考古
石杵(阿南市水井町)中野遺跡周辺) 9点
2.購入資料
●地学
こはく 1点
北投石ほか国内および外国産鉱物 6点
水鳥の足跡ほか外国産化石 4点
木の葉化石 16点
しのぶ石 1点
プシッタコサウルス 1点
輝安鉱 1点
コウイカの甲の化石 1点
補修痕があるペリスフィンクテス 4点
レバノン産板鰓類化石* 4点
アメリカ産恐竜の歯 4点
ドイツ・メッセル産動物化石 4点
チリ産カグラザメの歯化石(セット標本) 1点
●歴史
御鷹狩図 1点
蜂須賀正武書状 1点
蜂須賀家武具・調度品 4点
緒方家文書複製 1点
菅生家文書複製 2点
●民俗
日本山海名産図会 5点
水産事項特別調査 1点
引札 11点
●美術工芸
武内宿禰図絵馬* 渡辺広輝筆 1点
桜に鷹図 中山養福筆 1点
鯉図 松浦春挙筆 1点
扇散模様料紙硯箱 谷田蒔絵 1点
源氏物語夕顔図* 守住貫魚筆 1点
守住家画稿類* 3,763点
刀 銘 阿州泰吉作 1点
短刀 銘 阿州藩井上(以下不明) 1点
短刀 銘 阿州横山彦兵衛慶定 享和元年五月日 1点
梅山水図 河野栄寿筆 1点
(*印は平成15年度博物館資料収集委員会における審査資料)
購入資料合計 3,846点
3.寄贈資料
●動物(脊椎動物)
飯尾川産魚類業本 104点 徳島県河川課
宍喰川産魚類標本 49点 徳島県河川課
鴨島町壇池産他魚類標本 61点 徳島県農山村整備課
ニホンカモシカ 1点 徳島県文化財課
日和佐町奥方川産他魚類標本 222点 徳島県河川課
タウナギ 1点 吉田正隆氏
徳島県産鳥類 多数 日本野鳥の会徳島県支部
愛知県産ナガレホトケドジョウ標本 1点 洲澤 譲氏
水産学会誌ほか学術雑誌バックナンバー多数 吉田勝彦氏
由岐町産エラブウミヘビ標本 1点 浜野龍夫氏
園瀬川産魚類標本 2点 鍋島 昇氏
藍住町産キツネ 1点 藍住町保健衛生課
牟岐川産他魚類標本 271点 徳島県農山村整備課
岡山県産アナグマ剥製 1点
タヌキ 1点 徳山 豊氏
マミジロ 1点 松浦小夜子氏
ハイタカおよびアオゲラ 2点 吉田和人氏
旧吉野川水系産他魚類標本 46点 徳島県農山村整備課
ムササビ 1点 竹部秀信氏
故蜂須賀正氏氏蔵書 703点 蜂須賀正子氏
ヒメアマツバメ雛鳥 1点 吉成宏征氏
日和佐町沖から得られたクーズーの角のニュース映像ビデオテープ 1点 四国放送
ハイタカ 1点 東條秀徳氏
蜂須賀正氏氏関係文献 2点 森中定治氏
吉野川産イドミミズハゼ他標本 3点 国土交通省徳島河川国道事務所
ヤブサメ 1点 坂口正男氏
アオサギ 1点 吉田和人氏
宍喰町産ドンコ写真 3点 山下正和氏
物部川産魚類標本 多数 高橋弘明氏
チョウゲンポウ 1点 太田尚子氏
ハイタカ 1点 成田愛治氏
北島町産魚類標本 多数 徳島県農山村整備課
トラフズク 1点 井戸浩之氏
ノウサギ 1点 白井啓二氏
山城町白川谷川産魚類標本 1点 徳島県河川課
ヒメアマツバメ巣 2点 (財)徳島県文化振興財団
城ヶ島産シビレエイ 1点 山田和彦氏
●動物(無脊椎動物)
徳島県産甲虫類標本 369点 内田 清氏
徳島県産昆虫類標本 1,878点 桑野公男氏
飯尾川産無脊椎動 178点 徳島県河川課
徳島県産水生無脊椎動物 530点 フジタ建設コンサルタント
丸亀沖産無脊椎動物 36点 横川浩治氏
●植物
シダ植物標本 1点 関原菊太郎氏
バタン島産ススキ属標本 1点 船越英伸氏
セイヨウウキガヤ,タツノヒゲ 3点 田渕武樹氏
徳島県産標本 多数 佐治まゆみ・成田愛治氏
コンニャク果実 標本 1点 内藤禎蔵・ツヤ子氏
ウキガヤ属・ススキ属 各1点 木下 覚氏
生物季節観測用ススキ標本 1点 井関俊郎氏ら
海南町産植物標本 4点 斎藤 正氏
フタバガキ科など果実標本 7点 佐々木健志氏
ベトナム・インドネシア産種子標本 多数 西山保典氏
ヌメリグサ属植物 1点 木村氏
ススキ標本 1点 酒井氏
ハマナタマメ果実 1点 池渕正明氏
ダイズ 1点 大杉 桂氏
沖縄県産種子 3点 嵩原建二氏
スナシバ標本 1点 黒沢高秀氏
植物標本 107点 大阪市立自然史博物館
スミレ属標本 1件 山田直毅氏
スミレ属標本 1件 佐藤荷澄氏
スミレ属標本 1件 伊藤美代氏
フクジュソウ他 2点 西 郵局氏
●地学
勝浦町貝・アンモナイト化石 10点 大地晴明氏
石灰岩ほか化石・岩石 9点 松村良弘氏
勝浦町および高知県産化石 7点 西川忠行氏
上部蝦夷層群産バキュリテス 65点 辻野泰之氏
日本各地の中新世〜更新世貝化石 25点 吉田浩一氏
高知県室戸市産クジラ化石 1点 鎌田誠一・西川忠行氏
高知県室戸市産クジラ化石 1点 六久保美智子氏
紀伊水道産ノコギリガザミ化石 1点 高橋美津子氏
建築用石材 24点 徳島石材産業(株)
アンモナイト化石 1点 神元 勉氏
南部北上山地産古生代化石 5点 藤田吉広氏
エクロジャイト 2点 神野 裕之氏
鳴門海峡海底産ナウマンゾウ・貝化石 約15点
小野 守氏
高知県産鮮新世浮遊性巻貝化石 19点 三本健二氏
マダガスカル産前期白亜紀アンモナイト(修復痕あり) 1点 佐藤 征氏
北海道産後期白亜紀アンモナイト 4点 後藤栄治郎氏
淡路島産リビコセラス(白亜紀アンモナイト)完模式標本 1点 高田雅彦氏
北海道産後期白亜紀アンモナイト 6点 福岡 幸一氏
高知県産鮮新世貝化石 5点 高橋 節氏
石材サンプルおよびカタログ 5点 (株)梅彦
●考古
前山遺跡出土埴輪片・須恵器片 51点 大平馬喜太氏
●歴史
阿波おどり衣装 3点 砂子久雄氏
古式拳銃ほか 22点 田中利子氏
尋常小学校教科書ほか 171点 元木康夫氏
火縄銃 1点 藤井伸生氏
板碑拓本 10点 竹條教悟氏
●民俗
祭り用屋台ほか 10点 藤川廣士氏
携帯竿秤 5点 岩佐 春香氏
手動式計算機 2点 佐藤 久子氏
赤だる 3点 中島芳雄氏
4.寄託資料
●考古
平型銅剣 2点 神山町長
重郭文軒平瓦 1点 坂本 恵氏
神山町東寺銅剣 3点 山根文雄氏
袈裟襷文銅鐸(安都真出土) 4点 高橋浪子氏
●歴史
蜂須賀家船旗ほか 3点 福田宰大氏
阿波鳴門真景図 1点 武田和昭氏
菅生文書ほか 4点 内田英明氏
●民俗
花火製作関連資料 6点 仁木精一氏
賤が嶽七本槍三段目政右衛門(初代天狗屋久吉作)ほか 3点 四国放送
●美術工芸
丹生明神画像ほか 4点 黄田博司氏
丈六寺百川画賛ほか 20点 鬼田洋一氏
5.資料の貸し出し
●動物
メダカ・カダヤシ模型 1点 富岡小学校
イタチ剥製 1点 四国放送
クーズー角 1点 四国放送
アオギス他デジタル画像 3点 徳島県鳴門土木事務所
ツルグレン装置 5台 川内北小学校
●地学
勝浦町産出イグアノドン歯化石(複製)ほか化石標本 22点 海南町立博物館
ニホンムカシジカ(角) 1点 きしわだ自然資料館
●考古
若杉山遺跡出土品 2点 山城町石の博物館
火おこし道具・復元青銅器・石鏃 44点 上勝中学校
火おこし道具 6点 川島高等学校
火おこし道具 12点 栃之瀬小学校
袈裟襷文銅鐸ほか 9点 徳島市教育委員会(徳島市立考古資料館)
銅鏡・銅鏃・鉄製武器 32点 徳島市教育委員会 (徳島市立考古資料館)
●歴史
徳島大空襲関係資料 37点 ピースアクション2003
徳島大空襲関係資料 34点 四国放送
徳島大空襲関係資料 37点 川内中学校
徳島大空襲関係資料 37点 岩脇小学校
徳島大空襲関係資料 37点 上八万小学校
徳島大空襲関係資料 11点 上八万小学校
●美術工芸
越前国白山真景図 守住貫魚筆 1点 石川県立歴史博物館
みとものつら絵巻 村瀬魚親筆 2点 社団法人霞会館
刀 阿州住氏吉ほか 6点 海南町立博物館
●民俗
天狗久障子絵ほか 20点 徳島市立徳島城博物館
6.資料の交換
●植物(受入数)
東北大学(TUS) 260点
北海道大学 (SAPS) 121点
福島大学 (FUKU) 119点
7.館蔵資料数
平成16年3月末日現在の分野別収蔵資料数は次表のとおり。
収蔵資料については、整理、標本作製等がすんだものから順次コンピュータ入力し、資料データベースを作成している。
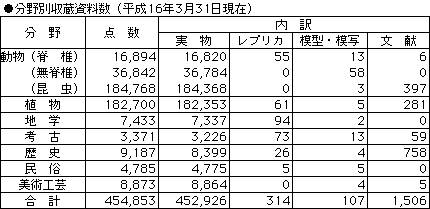
8.資料収集委員会
館長の諮問に応じて博物館における購入資料について審査する機関として、博物館資料収集委員会が設置されている。本委員会は、「美術品等取得基金による美術品等の取得要領」の規定に従って、200万円以上の購入資料について審査する。
委員は常任委員(5名以内、任期2年)と特別委員(3名以内)から構成されており、特別委員は、購入資料に応じて特に必要がある場合にその都度委嘱される。
本年度は、平成16年2月6日に第17回委員会を開催し、「1.購入資料」にリストした人文資料3件および自然資料1件の購入を諮問した。
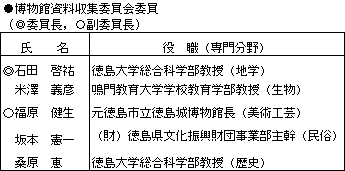
9.文献資料の収集
文献資料から得られる情報は、調査研究にはもちろんのこと、展示や普及教育などの博物館活動全般にわたるレベルアップをはかる上で不可欠である。当館では、人文・自然史分野の専門書や学会誌のほか、徳島県を中心とした地方史誌類や普及教育用図書も収集している。また、内外の博物館等の研究報告・年報・展示解説書等も交換により収集している。
●購入図書冊数(デ−タベ−ス登録数)
11,600冊(平成15年度分 339冊)
●購入雑誌
自然史系(26タイトル):生物科学、科学、日経サイエンス、海洋と生物、月刊海洋、遺伝、プランタ、月刊むし、昆虫と自然、地学雑誌、月刊地球,
American Journal of Botany, Cladistics, Episodes,
Evolution, Geology, Journal of Evolutionary Biology,
Journal of Paleontology, Nature, Paleobiology, Plant
Systematics and Evolution, Science, Systematic Botany,
The American Naturalist, Trends in Ecology and Evol.,
Lethaia, Palaeontology
人文系(34タイトル):美術研究、美術史、佛教芸術、地方史研究、地理、芸術新潮、芸能史研究、月刊考古学ジャーナル、月刊文化財、月刊文化財発掘出土情報、季刊考古学、考古学と自然科学、古文化財の科学、古代文化、古代学研究、国華、古文書研究、考古学研究、考古学雑誌、九州考古学、民族学研究、日本の美術、日本民俗学、日本歴史、日本史研究、歴史学研究、歴史評論、歴史と地理、歴史地理学、史林、史学雑誌、信濃、Folklore,
Journal of American Folklore
●当館刊行物の定期発送先(平成16年3月末現在)
博物館ニュース 1,427ヶ所
博物館年報 492ヶ所
研究報告 国内 551ヶ所
国外 152ヶ所
展示解説 238ヶ所
企画展図録 自然 132ヶ所
人文 236ヶ所
10.資料の燻蒸
収集した資料、貸し出し後返却された資料は、原則としてすべて収蔵庫への搬入、展示に先だって燻蒸を行う。
当館では資料の形態や量などによって、次の3種類の燻蒸を行っている。
●減圧燻蒸装置による燻蒸
小型資料の燻蒸は、資料の受け入れのつど、担当学芸員が減圧燻蒸装置を使って行う。減圧燻蒸装置の有効内寸は、たて130cm×よこ120cm×奥行140cm(約2.3ɠ)で、燻蒸剤には臭化メチルと酸化エチレンの混合ガスを使用している。
15年度は18回の減圧燻蒸装置による燻蒸を行った。
●常圧燻蒸庫での燻蒸
減圧燻蒸装置に入れることができない大型の資料は、一時保管庫(24時間空調)に仮収蔵し、資料が適当な量になった時点で常圧燻蒸庫で燻蒸する。
常圧燻蒸庫は床面積20ɠ×高さ3m(約60ɠ)であり、燻蒸は文化財専門の燻蒸業者に委託し、燻蒸剤には臭化メチルと酸化エチレンの混合ガスを使用している。
15年度は、3回の常圧燻蒸庫での燻蒸を行った。
●収蔵庫の全室密閉燻蒸
収蔵庫への出入りなどにともなって、害虫やカビなど資料の保存に悪影響を与えるものが侵入することがある。そのために、原則として3年に1回、専門業者に委託して収蔵庫の全室密閉燻蒸を行っている。
前回は14年度に実施したため,15年度は実施していない。
|