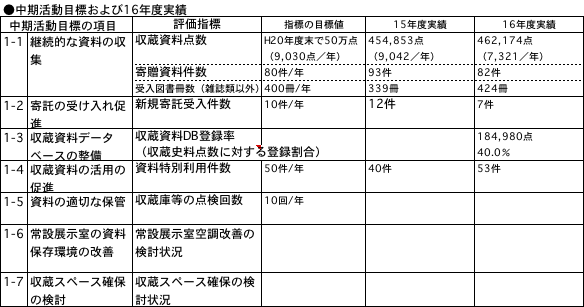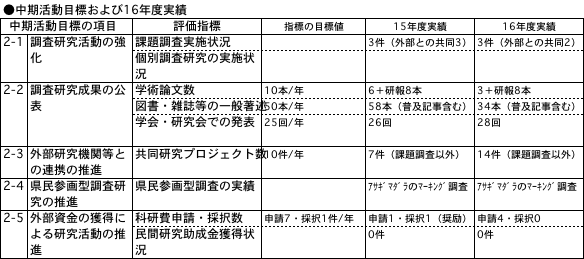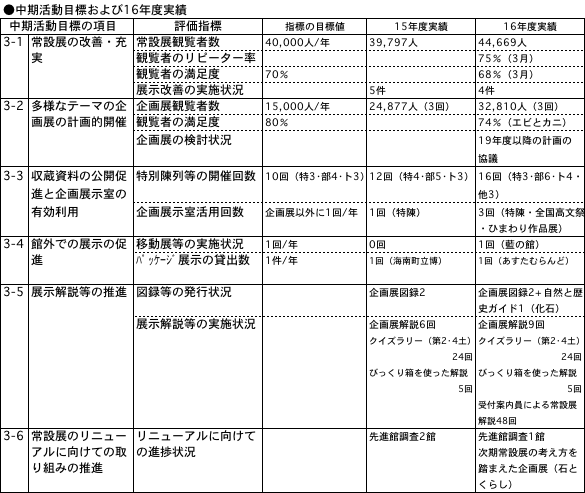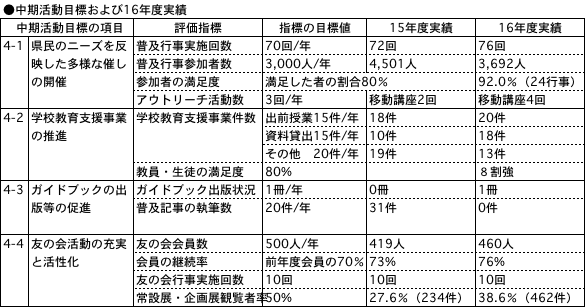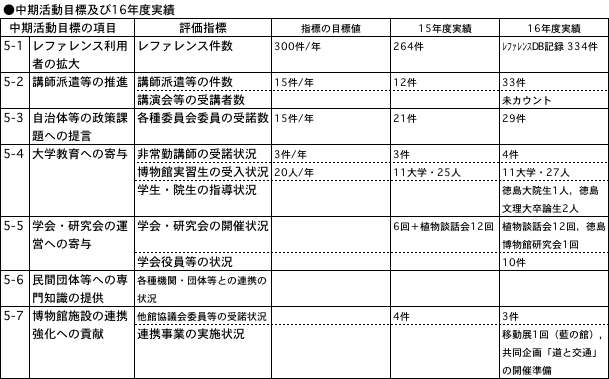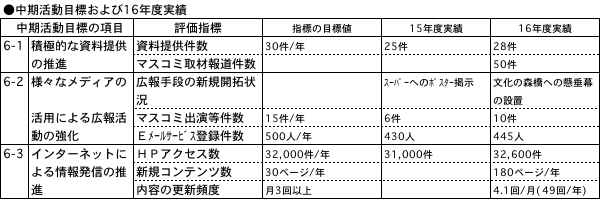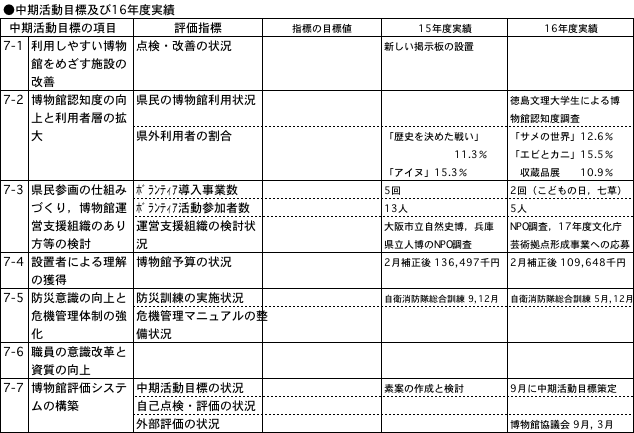|
徳島県立博物館の中期活動目標
16年度実績と自己点検・評価
1.資料の収集・保存と活用
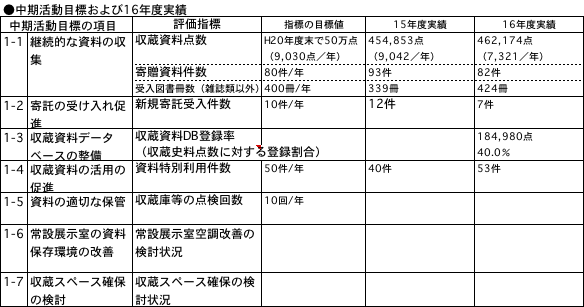
<1-1>
・H15年度を基準とした収蔵資料点数の年度増加目標値は1,709点下回った。しかし、資料増加点数は年度ごとのばらつきが非常に大きいので(標準偏差25,807点、開館以来の実績値に基づく)、全体的にみれば16年度がとくに低かったとはいえない。
・寄贈資料件数は、目標値より2件多く、ほぼ平年並みであった。
・受入図書冊数は予算に依存しているため、予算が縮小している中では今後の目標達成は困難と思われる。
<1-2>
・新規寄託受入件数は、目標値より3件少なかったが、ほぼ平年並みと思われる。
<1-3>
・当初、評価項目として収蔵資料DB登録率のみをあげていた。しかし、受入資料の総点数が不明なため、当初から算出不能性が問題となっていた。新たに収蔵資料DB登録数の項目を設け、推移をみて今後目標値を設定したい。ここに示した収蔵資料DB登録率は、収蔵資料DB登録数を単に1-1の収蔵資料点数で割った参考値である。大きなコレクションを受け入れると、登録率は低下してしまうので、現時点ではこの基準で目標値を設定することは妥当でないと考えられる。
<1-4>
・資料特別利用件数は、目標値より3件多く、ほぼ平年並みであった。
・なお、資料特別利用件数には貸出以外の件数も含まれている。しかし、年報にはこの指標のうち貸出資料の記載しかなく、両者の対応付けを今後ははかるべきだろう。
<1-5>
・収蔵庫等の点検回数は、実施要領がまだ定まっていないので、今回は評価できなかった。
<1-6>
・常設展示室は、収蔵庫のような密閉可能な空間でなく、展示室全体の燻蒸が不可能なため、害虫などの侵入による資料の劣化の可能性が大きい。実際、植物乾燥資料等で害虫が確認されている。
・常設展示室内の空調は温度設定のみ可能で、湿度のコントロールができない。そのため、時期によってはカビの発生が懸念される。
・常設展示室の構造的・設備的な問題であるので、現時点では抜本的な対策およびその検討はなされていない。
<1-7>
・鳥居記念館資料の受入に当たり、収蔵スペースが著しく不足することが予想されたため、保存処理室1の転用を検討した。予算の確保が最大の課題。
・不定形で大型の資料の多い民俗分野では、すでに収蔵スペースがほとんどなく、考古収蔵庫の空きスペースを流用している状況である。
・民俗分野以外でも、収蔵スペースに余裕がなくなりつつあることから、収納方法を工夫するなどして対応している。今後、何年間で収蔵スペースがなくなるのか、その見通しを分野ことに検討していく必要がある。
2.調査研究
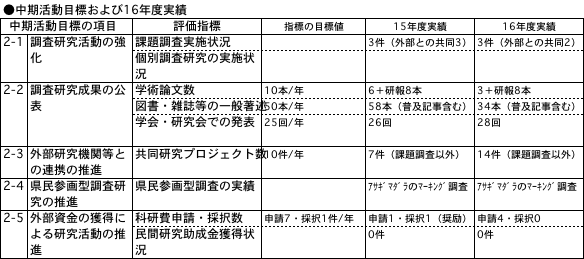
<2-1>
・課題別、分野別に調査研究を実施し、それぞれ成果をえた。
<2-2>
・成果の公表数では学芸員毎に偏りがみられた。
<2-3>
・外部研究機関から要請のあった共同研究が多くみられた。
<2-4>
・新規プロジェクトの企画が必要である。
<2-5>
・より積極的な取り組みが必要である。
3.展示
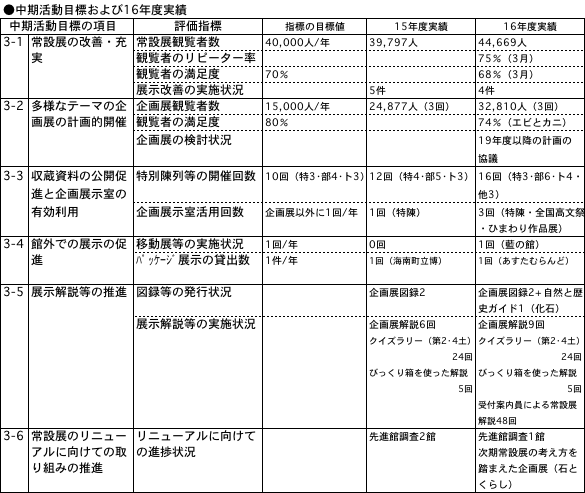
<3-1>
・常設展観覧者数は44,669人で、目標を上回った(前年度比4,872人増)。企画展開催月における観覧者数が増加しているので、3−2で触れる企画展観覧者数の増加が影響していると考えてよいだろう。また、閑散期にあたる12・1月の観覧者数が増加している(12月;前年比839人増、1月;同419人増)ことも注意される。この時期の部門展示(人文)が新聞で報道されたことなどが影響したものと思われる。
・今年度の利用状況調査(3月実施)では、リピーター率は75%であり、継続的な利用者が多数を占めていることがわかった。
なお、新規利用者が絶えず得られることも必要であるため、リピーター率については高いほどよいというものではない。
・総合展示を中心とする展示の改善件数(部門展示[人文]の展示替えを除く)は前年度並みで、わかりやすく親しみやすい展示、新鮮な展示を目指したが、観覧者に浸透するほどではなかったようである。観覧者調査でも、「変わらない」という印象が強く、満足感を示した者は目標に満たなかった。常設展の全面リニューアルが困難な中だけに、新鮮さを感じ、見てよかったと思えるような展示とするにはどのような改善方法があるか、検討を重ねていかなくてはならない。
<3-2>
・「サメの世界」「エビとカニ」がとくに多数の観覧者を得たため、企画展観覧者数は32,810人で、目標の2倍以上あった。前年度と比べても8,000人弱の増加となっている。 ・企画展は、テーマとタイミングがうまくマッチすれば大量動員が可能になるが、その見極めは難しい。娯楽性、新規性、学術性等の諸要素を取り合わせた計画的運営が求められるところだが、予算の見通しが立たない状況のもと、将来的な開催計画についての検討は不十分である。
・観覧者の満足度を調査したのは「エビとカニ」の1回だけだが、総合的に満足感を示した割合は74%であった。目標値に満たなかったものの、質的にも一定の評価が得られたものと見てよいだろう。
<3-3>
・特別陳列等の開催回数は16回あり、目標の10回を大きく超えている。ただし、そのうち2回は教育委員会関係事業への企画展示室の提供であり、また、特別陳列のうち2回は、近代美術館ギャラリーを会場とする文化の森人権啓発展である。これらを差し引いた博物館独自の取り組み回数は12回となる。
・15年度から始めた、部門展示(人文)の計画的な展示替え、トピック展示の開催は、今年度も継続した。これらの展示替えコーナーを目的にした観覧者もあることから、一定の成果を挙げていると考えられる。
<3-4>
・移動展、パッケージ展示の貸し出しは、今年度とくに意識的に取り組みを進めた。パッケージの貸し出しについては、県内の博物館等に案内チラシを配布して、活用を呼びかけた。結果的に移動展、パッケージ展示ともに1件ずつ実現し、目標を達成できた。
・移動展については、簡単には来館できない遠隔地住民へのサービス強化や地域振興への協力の観点から、今後取り組みを強化する必要がある。
<3-5>
・長らく常設展の内容に関する冊子の発行ができていなかったが、今年度は常設展の化石を取り上げた『徳島の自然と歴史ガイド』が刊行できた。今後も継続的に取り組んでいきたい。
・展示解説等については、昨年度までのものに加え、受付案内員による常設展解説を行ったことが新しい取り組みである。今後の課題として、部門展示(人文)やトピック展示などの、常設展における期間限定の展示を行うコーナーの解説や利用に力を入れることが挙げられる。例えば、クイズラリーの設問としての活用、企画展で恒例となっているのと同様、担当学芸員による展示解説の実施などの取り組みを検討すべきである。
・常設展示室の活性化や新しい利用方法について、利用者の目線に立って考えていくため、ボランティアの導入について検討を進めた。
<3-6>
・財政状況がきわめて厳しい中、常設展更新については、到底、関係方面の理解が得られる状況ではない。事業としては大きな進展を見ないとしても、これまでに検討した次期常設展の考え方を活かしながら、現行常設展の手直しや企画展を意識的に行って、内容を煮詰めていく努力が必要である。また、先進館調査を継続し、絶えず博物館の新しい展示動向を抑えるよう努めている。そうした経験や調査成果を、学芸員全体で共有する態勢づくりが不十分であることは否めないので、今後の取り組み方を検討していきたい。
4.普及教育
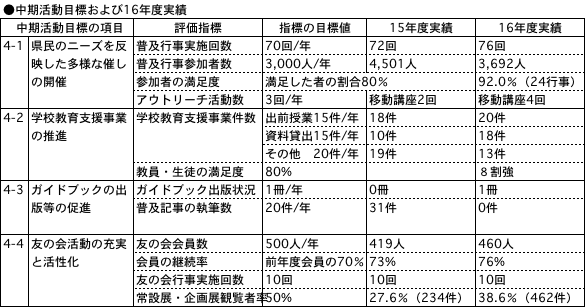
<4-1>
・普及行事参加者の満足度は、24行事で行ったアンケート結果から出したが、おおむね好評であった。
<4-2>
・学校教育支援事業について詳しく知らない教職員も多い。今後、広報に力を入れなければいけない。
<4-3>
・ガイドブックを1冊出版した。新聞・雑誌の普及記事執筆については、相手からの要望を待つだけでなく、機会あるごとにこちらから働きかけていくことも必要である。
<4-4>
・友の会では、会員数・継続率ともに順調に推移している。また、行事では、会員の自主的な運営へと徐々に移行することができている。
5.シンクタンクとしての社会貢献
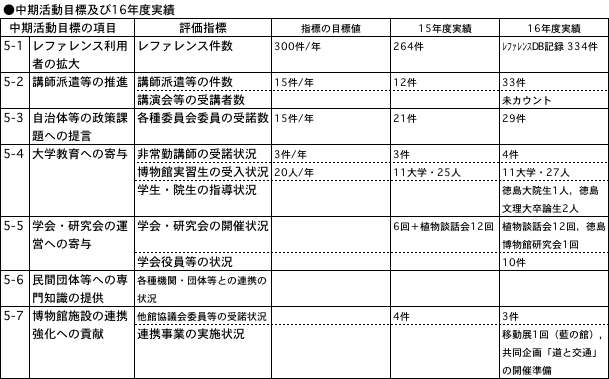
<5-1>
・レファレンスが増えている。これは博物館の存在と役割が県民に浸透してきている結果として評価できる。記録として残されないものが相当数に及ぶと思われるので、きちんと記録することを心がける必要がある。
<5-2>
・講師派遣依頼が増えている。依頼が特定の分野の学芸員に集中することはある程度避けがたいが、当館学芸員の重要な社会貢献の一環として、可能な範囲で前向きに対応することとしたい。
・受講者数のカウント・記録方法を検討する必要がある。
<5-3>
・各種委員等への委嘱依頼が増えいている。特定の分野の学芸員に集中することはある程度避けがたいが、当館学芸員の重要な社会貢献の一環として、可能な範囲で前向きに対応することとしたい。
<5-7>
・当館は、徳島県博物館協議会の事務局を務めるほか、県内博物館施設の連携強化に大きな役割を果たしている。
6.情報の発信と公開
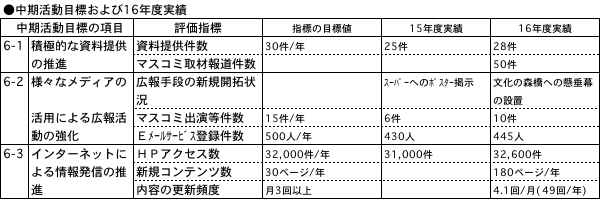
<6-1>
・資料提供件数は目標の30件/年には達しなかったものの、前年より多くなっている。博物館からのより効果的な情報発信として、マスコミに対する資料提供を今後とも積極的に続けていく必要がある。
・マスコミ取材・報道件数については新聞のみの数であるが、50件となっており、活発な取材や報道が行われていることが伺える。
<6-2>
・広報手段の新規開拓状況では文化の森橋への企画展開催の懸垂幕の設置を行った。良く目立つ位置にあり、来館者に対する広報効果も高いので今後とも続けていくことが望まれる。
・マスコミ出演等件数やEメールサービス登録件数は前年度より増加しているものの目標値に達していないので、今後の努力が必要である。
<6-3>
・インターネットによる情報発信はすべて目標値に達しており、良い状態である。ただ、発信している情報に偏りがあり、より広い内容での発信が求められている。
7.マネージメント
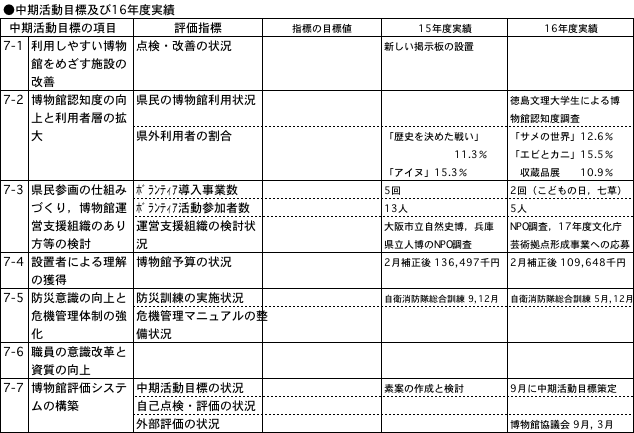
<7-1>
・16年度は特段の取り組みは行われなかった。
<7-2>
・徳島文理大学生2人の卒業研究の一環として同大学生に対する博物館認知度調査が行われ、当館が協力した。
<7-3>
・当館では普及行事の補助スタッフとしてボランティアを導入しているが、積極的な導入とは言い難い。展示や調査研究など普及行事以外での県民参画についても取り組む必要がある。
<7-4>
・館運営予算は15年度より約27,000千円減少した。企画展開催経費約4,000千円の削減、資料購入費の削減と執行保留による約23,000千円の減少が主たる要因である。
・17年度は企画展開催経費が更に削減されることになっており、苦しい運営を余儀なくされている。
<7-5>
・法令で定められた年2回の防災訓練は行われているが、内容がマンネリ化している嫌いがある。
・火災・地震、盗難等の防災、停電、けが人や病人等の発生等に備えた総合的な防災マニュアルの作成が急がれる
<7-6・7-7>
・9月に「徳島県立博物館の中期活動目標」を策定したことは、全国的にも先駆的な取り組みとして評価できる。
・中期活動目標を単なる作文に終わらせないよう、活動目標を意識した実践、自己点検・評価をきちんと行い、博物館活動の改善・活性化に結びつけるという方向で、全職員がいま一層の意識統一を図ることが大切である。
|