2005年博物館実習
博物館の情報発信
2005年8月26日(9:30-12:00)に「博物館の情報発信」について実習を行いました。なお、「情報」についての定義は時間がないので明確にせず、「発信」については、コンピュータによるものに限定しました。

1.講議
インターネットによる情報提供(平成16年度年報より)
(1)電子メール
希望者には電子メール(以下メール)による催し物案内を毎月行っている(17年3月末現在の登録者445名)。
また,ホームページ等を見た人からの質問もメールで寄せられており,各担当より回答を行っている。平成16年度には記録されたものだけでも30件の問い合わせが寄せられている。
(2)ホームページ
インターネット利用者の増加に伴い、博物館でもその技術を活用した情報提供の可能性を探ってきた。平成11(1999)年7月よりホームページ(http://www.museum.comet.go. jp/)を開設した。トップページのアクセス数の累計および1日あたりのアクセス数は図のとおりである。どちらも順調に増加しており,平成16年度1年間でトップページに約32,600件のアクセスがあった。
ホームページの内容は下記のとおりである。
・博物館の紹介(開館日・交通案内など)
・展示案内(企画展、常設展)
・催し物、普及行事の案内
・調査研究活動の紹介
・収集保存活動(データベース)
・学校等への利用案内
・出版物(展示解説、研究報告、博物館ニュースなどの案内)
・関連活動紹介(友の会、博物館協議会など)
・学芸員関連のページ
・特別メニュー(子供向けメニュー、映像コーナーなど)
ホームページには内容の全文検索やサイトマップを設置し,閲覧者が目的の内容にたどり着きやすくしている。全文検索についてはシソーラス(同義語)辞書を用いて,たとえば,「やまざくら」,「山桜」,「ヤマザクラ」などの言葉で,検索しても検索できるようにしている。
データベースによる検索では,資料データベースでは人文,動物,植物,地学の各分野ごとに収蔵資料を検索でき,資料の写真や動植物の分布図などが表示できる。また,当館に収蔵している図書についても,図書デ−タベ−スを公開している。情報提供する項目のテキストデータおよび画像情報を専用フォルダーに入れておけば、夜のうちに自動的に情報提供用のデ−タベ−スに取り込まれる仕組みになっている。
ホームページの更新や追加は毎月の催しもの案内のように定期的に行うもののほか,各担当により随時行っている,平成16年度の追加内容については下記のとおりである。
・「徳島県立博物館の新たな試み」として,毎年発行している年報や博物館協議会の議事録をホームページ上でも公開した。また,平成16年9月9日に作成した中期活動目標についても掲載した。
・県民から広く博物館運営等に意見を収集するために,「ご意見コーナー」を設置した(2005年3月18日).「ご意見コーナー」に投稿された内容は,とりまとめ者にメールで送信され,内容に応じて担当者に振り分け,そこからメールで回答を行っている。開設して日も浅いためになされた投稿は1件のみであったが,県内の棟札に関する情報が得られた.
・「デジタルミュージアム」を開設し,「渡辺広輝筆 光格上皇修学院御幸儀仗図巻(徳島県指定文化財)」や銅鐸等の貴重資料をホームページで閲覧できるようにした。また,美術工芸資料の紹介として,高精度画像を用いた資料紹介を行った。
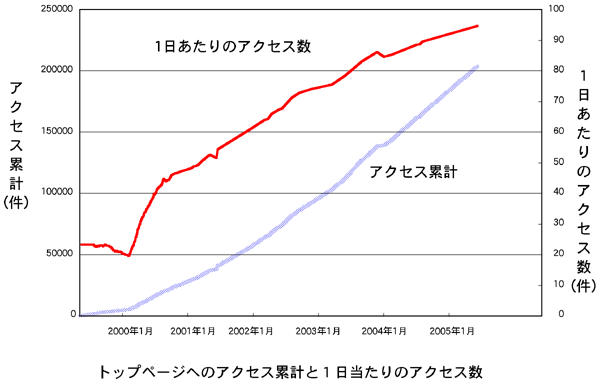
・ブロードバンド対応
・ブログの活用
・全文検索とサイトマップの設置
実習の資料(jisshu.pdf
925kb)
2.見学
・コンピュータ室
・レファレンスルーム
・研究室
・収蔵庫
3.実習
自分が受けてきた博物館実習に関するホームページの案を考えてもらいました。その中味を紹介します.

小川のページ
|