徳島県立鳥居龍蔵記念博物館

お気軽にお問い合わせください
TEL. 088-668-2544
開館時間 9:30 ~ 17:00
催し物
2025年度 催し物案内
 2025年度 催し物案内ができました。「鳥居龍蔵セミナー」など、ぜひご参加ください。
2025年度 催し物案内ができました。「鳥居龍蔵セミナー」など、ぜひご参加ください。
→催し物案内PDF
2025年度企画展 中国西南部の旅人 ─鳥居龍蔵と高原の少数民族─
鳥居龍蔵が中国西南部で行った調査について紹介します。
| 会 期 | 2026年1月31日(土)~3月8日(日) |
|---|---|
| 会 場 | 徳島県立博物館 企画展示室 |
展示解説
●日時:2026年2月7日(土)、2月28日(土)、3月8日(日)
いずれも 13:30~ 14:30
※企画展観覧料が必要です。
記念講演会①
●日時:2026年2月1日(日)13:30~15:00
●場所:文化の森イベントホール
●講師:鈴木正崇氏(慶應義塾大学名誉教授)
●参加無料、先着100名
記念講演会②
●日時:2026年2月22日(日)13:30~ 15:00
●場所:文化の森イベントホール
●講師:吉開将人氏(北海道大学大学院教授)
●参加無料、先着100 名
鳥居龍蔵セミナー
徳島出身の人類学・民族学・考古学の研究者である鳥居龍蔵の学説や調査活動などを、当館の学芸員らがそれぞれのテーマに沿って、わかりやすくお話しします。
1 2025年5月18日(日)「鳥居龍蔵の中国西南部調査と清末知識人」
坂東 泰(鳥居龍蔵記念博物館)終了しました
2 2025年6月29日(日)「鳥居龍蔵と三好市三野町で採集された大量の石鏃」
植地岳彦(鳥居龍蔵記念博物館)終了しました
3 2025年7月20日(日)「鳥居龍蔵の趣味と人となりについて」
小林篤正(鳥居龍蔵記念博物館)終了しました
4 2025年9月21日(日)「鳥居龍蔵の中国仏塔調査」
下田順一(鳥居龍蔵記念博物館)終了しました
5 2025年10月19日(日)「鳥居龍蔵の北京移住とその周辺」
長谷川賢二(鳥居龍蔵記念博物館)終了しました
●時間:各回とも 13:30~15:00
●場所:徳島県立博物館 講座室
●参加無料、先着50名
夏休みスペシャル みんなで発見 !! 鳥居龍蔵を知ろう !!
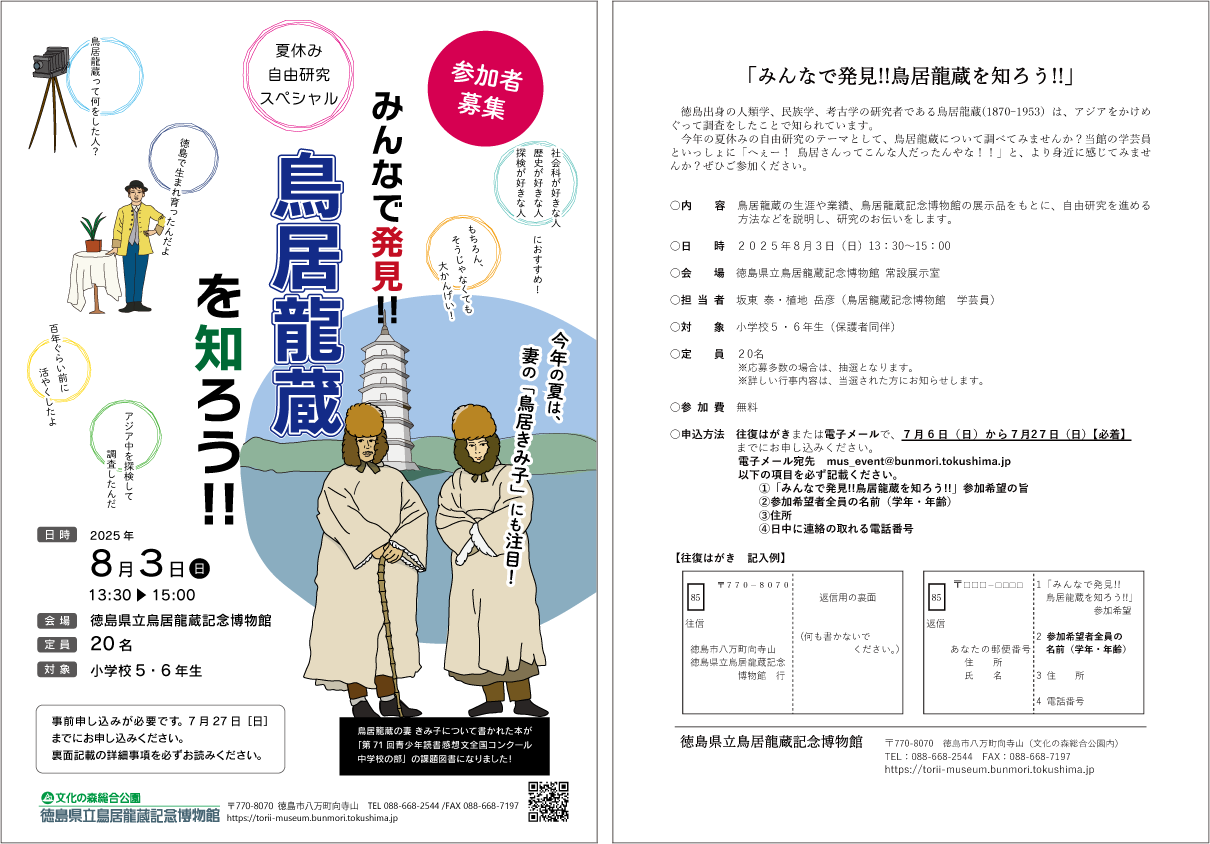 当館の学芸員と一緒に鳥居龍蔵について調べます。
当館の学芸員と一緒に鳥居龍蔵について調べます。
→チラシPDF
終了しました
鳥居龍蔵ゆかりの地を歩こう
当館の学芸員と一緒に、徳島市街地にある鳥居龍蔵ゆかりの場所を歩きます。
●日時:2026年3月22日(日) 9:30~12:00
●場所:徳島市内、現地集合
●定員:20名
●参加無料、申込が必要です。
申込方法は開催日の約1か月前にホームページに掲載します。
鳥居龍蔵記念 徳島歴史文化フォーラム
県内の中学生と高校生による、地域の歴史・文化に関する自主的な研究の成果を発表します。
●日時:2026年2月14日(土)
●場所:文化の森イベントホール
●参加無料、申込不要
鳥居龍蔵記念 全国高校生歴史文化フォーラム
全国の高校生と、徳島フォーラムでの優秀賞受賞者による、地域の歴史・文化に関する自主的な研究の成果を発表します。
●日時:2026年2月15日(日)
●場所:文化の森イベントホール
●参加無料、申込不要



