山本候充編『日本銘菓(めいか)辞典』【情報ボックス】
民俗担当 庄武憲子
あと1力月もすれば、梅雨(つゆ)も明け、夏休みとなります。休みを利用した旅行の計画を立て始めている方もいるのではないでしょうか?
さて、旅行につきものといったらおみやげで、このおみやげとしてしばしば求められるものに、その土地の銘菓と呼ばれるものがあると思います。昨年には、銘菓の中でも有名なものに、製造日の偽装(ぎそう)等が見つかったりして、残念なこともありましたが、銘菓には、その土地の特色にちなんだユニークなものが多く見られます。訪れた土地のイメージを、その土地の銘菓で再確認したリ、ほかの人に伝えたりする楽しさがあるかと思います。
紹介する『日本銘菓事典』は、その名の通り日本各地の銘菓を、都道府県ごとにまとめて紹介した事典です。菓子名、菓子の材料・形、販売している店舗(てんぽ)のほか、その菓子の出来上がった由来が記されています。お菓子を通じて、その土地柄(がら)が感じられる「お菓子の風土記(ふうどき)」的事典を目指したということです。順に目を通して行くと、さまざまな銘菓の存在を知ることができるのはもちろん、菓子の背景となった各地の風景や名所、特産物、歴史のミ二知識を得ることができます。また、販売品ではない土地に伝わる郷土菓子や、菓子に関する博物館や図書施設の紹介もあり、よその土地を知るちょっとこれまでにないガイドブックのような感じを受けます。
記載されている事例の中で、面白いと感じたものをあげてみます。
北海道旭川市(あさひかわし)の銘菓「-41℃(氷点下41℃)」はスライスアーモンドが北の大地、ホワイトチョコレートが白雪、最中がダイヤモンドダストを表現した菓子です。日本の気象史上、最低気温を旭川で、記録したため、その温度を菓子名にしたそうです。
富山県の「反魂旦(たんこんたん)」は江戸時代に富山の薬売りが全国に広めた、万病にきく丸薬「反塊丹(たんごたん)」を摸した一口饅頭(まんじゅう)です。丸薬に見立てて金色の紙で包装(ほうそう)し、薬売りがサービスに持ち歩いたサイコ口状の紙風船をおまけに付けているとされます。
佐賀県の「伊万里焼鰻頭(いまりやきまんじゅう)」は、陶器の伊万里焼きの風合いを表現した洋風焼き菓子で、ひびを入れる焼き上げで陶器(とうき)の感じを表しているそうです。包装も陶器の模様を生かしているとのことです。
どうでしょう?菓子への知識と共に、その土地のイメージを身近に感じられないでしょうか?
この本で少々残念なのは、徳島県の銘菓が12品しか記載(きさい)されていないことです。理由はよくわかりませんが、これはちょっと少ないような気がします。けれども、菓子を通して、よその土地のことを知り、全国各地にいろいろな特色があることをあらためて知ることのできる楽しい本だと思います。
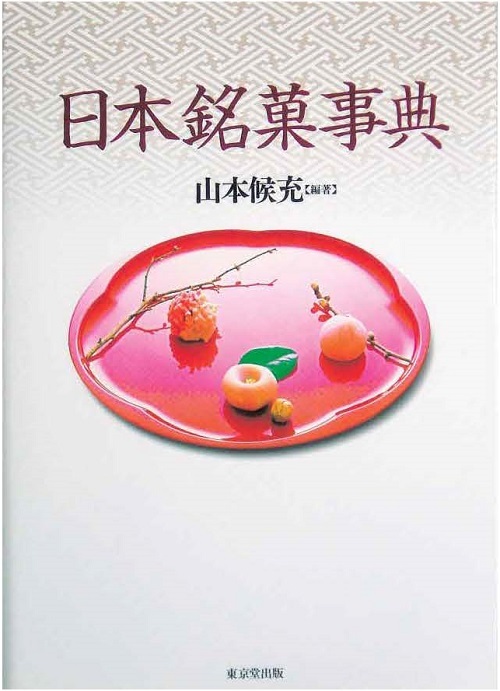
日本銘菓(めいか)辞典
